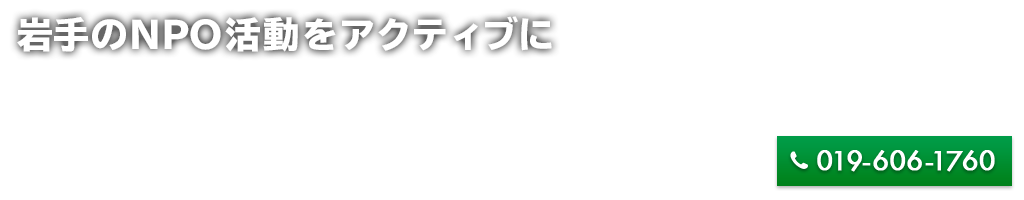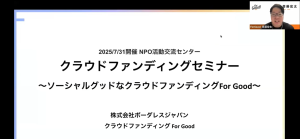【開催報告】第1回NPO運営基盤強化セミナー「NPOの“想い”を届ける資金調達術 ~助成金申請のコツとクラウドファンディング成功のヒント~」
NPO活動交流センターでは、県内NPOのニーズや支援の必要性に合わせた「NPO運営基盤強化セミナー」を開催しています。
第1回目は2025年7月31日(木)、日本郵便株式会社サステナビリティ推進部の竹山吾紀明さんと、
株式会社ボーダレスジャパン クラウドファンディングFor Good事業開発部の斎藤宏太さん(オンライン登壇)を講師に、
「NPOの“想い”を届ける資金調達術~助成金申請のコツとクラウドファンディング成功のヒント~」を開催しました。
初めに、NPO活動交流センターの葛巻より、NPOの多様な財源構造や関わり方について説明をし、
本講義の前提として、改めてNPOの運動性や社会的位置づけなどについてお話ししました。
続いて、竹山さんより日本郵便株式会社の年賀寄付金配分事業を基に、
「審査のポイント」「申請書作成のポイント」などについてもお話しいただきました。
審査のポイントとして以下が挙げられました。
・先駆性:先駆性が高く発展性のある事業
・社会性:社会的ニーズとその社会的波及効果の高い事業
・実現性:事業計画が明確化され、実現性が高く継続・発展が見込める事業
・緊急性:緊急性の高い事業
これらに加え、3つの定量的条件が加味されるとのことでした。
・申請配分額:申請配分額がより小さい方を優先
・自己負担率:申請事業の事業費総額に占める自己負担金の割合が大きい方を優先
・次期繰越剰余金:団体の前年度決算における次期繰越剰余金のより小さい方を優先
申請書作成のポイントとして、9つのポイントをお話しされ、中でもより大切だと感じたものを以下に記します。
・誰にでもわかる表現で:専門用語ではなく、中学生が理解できる言葉を。
・目的は何か:団体の説明を羅列するのではなく、実現したい未来を。
・要点は簡潔に、実施内容は明確に:課題を詳細に書くよりも、解決策を詳細に。
・予算の算出根拠は詳細に:一式●●万円ではなく、単価×個数で。
今回は、年賀寄付金配分事業の申請内容を基にお話しいただきましたが、
そのどれもが他の助成金・補助金の申請にも活かせるもので、
参加者からは「審査員が見る部分がわかってよかった」「助成金を出す側がどのようなポイントを重視しているのかがわかり、大変参考になった」などの声をいただきました。
最後に、斎藤さんよりクラウドファンディング自体の説明と、プロジェクトの事例・成功の鍵をお話しいただきました。
クラウドファンディング(以下、クラファン)とは、実現したいプロジェクトに共感した方々から
インターネットを通じて資金の支援を募ることが出来る仕組みのことです。
大きく分けて、商品やサービスを提供し、その代わりに資金を募る「購入型(一般型)」と、
リターンは特に設定せず寄付を募る「寄付型」の2種類があります。
成功の鍵としては、以下の4つに分けて具体的にお話しいただきました。
・基本姿勢編:「クラファンを実施すれば、勝手にたくさんのお金が集まりそう!」「とりあえずクラファンでお金を集めて、使い道は後から考えよう!」というのは誤解と失敗で、入念な準備こそが達成の鍵になる。
・ページ作成編:共感してもらうために、想いを「読みやすい形」で伝える。解決したい課題を具体的に伝える。
・リターン編:リターン設計でのポイントは「支援者の顔を思い浮かべること」
・広報編:お金集め<共感集め。クラファン開始前・直後・中間時期・終了直前など全てのタイミングで広報が重要。
クラファンを始める前に整理したいポイントとして、
・「何のために」「なぜ」クラファンを選ぶのか?
・支援者の人に伝えられる想いはあるか?
が非常に重要だと、改めて感じました。
参加者からは「クラウドファンディングについて、難しそうと当初思っていましたが、
具体的な例を用いて説明いただけた為とても理解しやすく、チャレンジできそうと思えた。」などの声をいただきました。
本セミナーは、参加者39名(来場:14名、オンライン:25名)にご参加いただきました。
ご参加いただいたみなさまありがとうございました。
次回は、第2回セミナー「共感を呼ぶ企画書づくり~NPOのための事業構築と連携の第一歩~」について報告いたします。